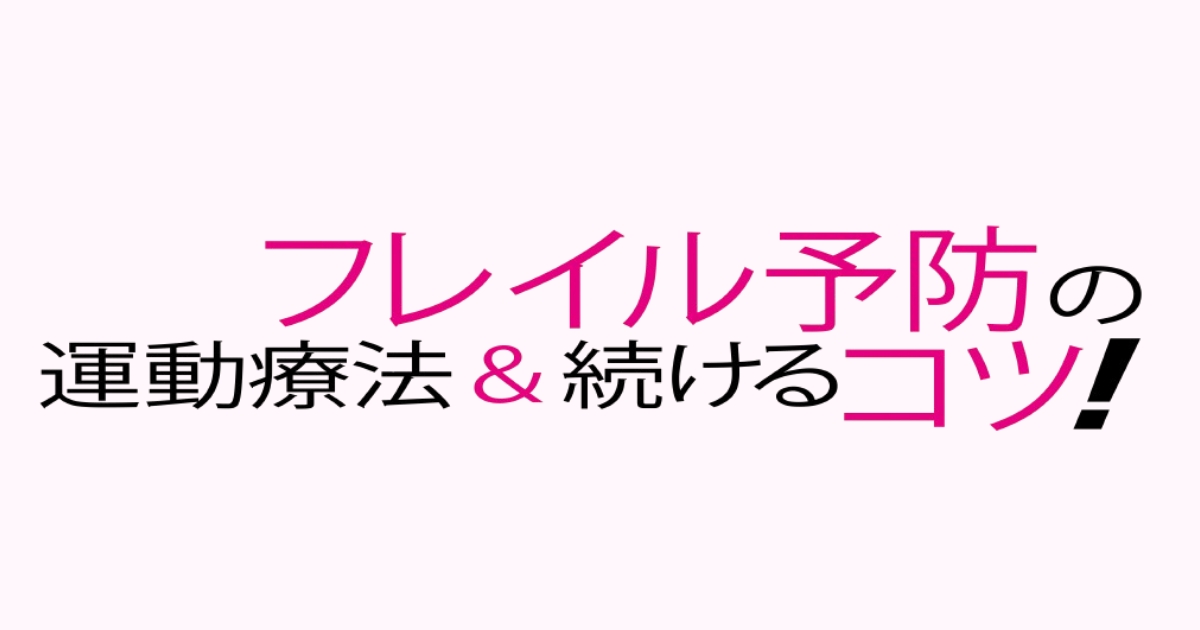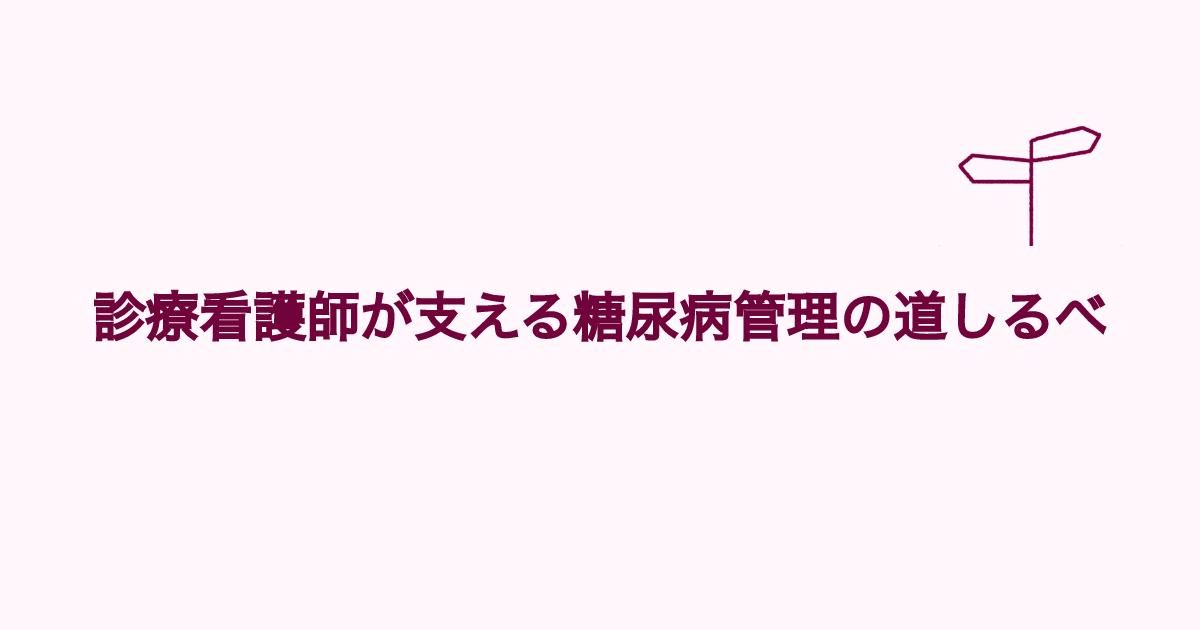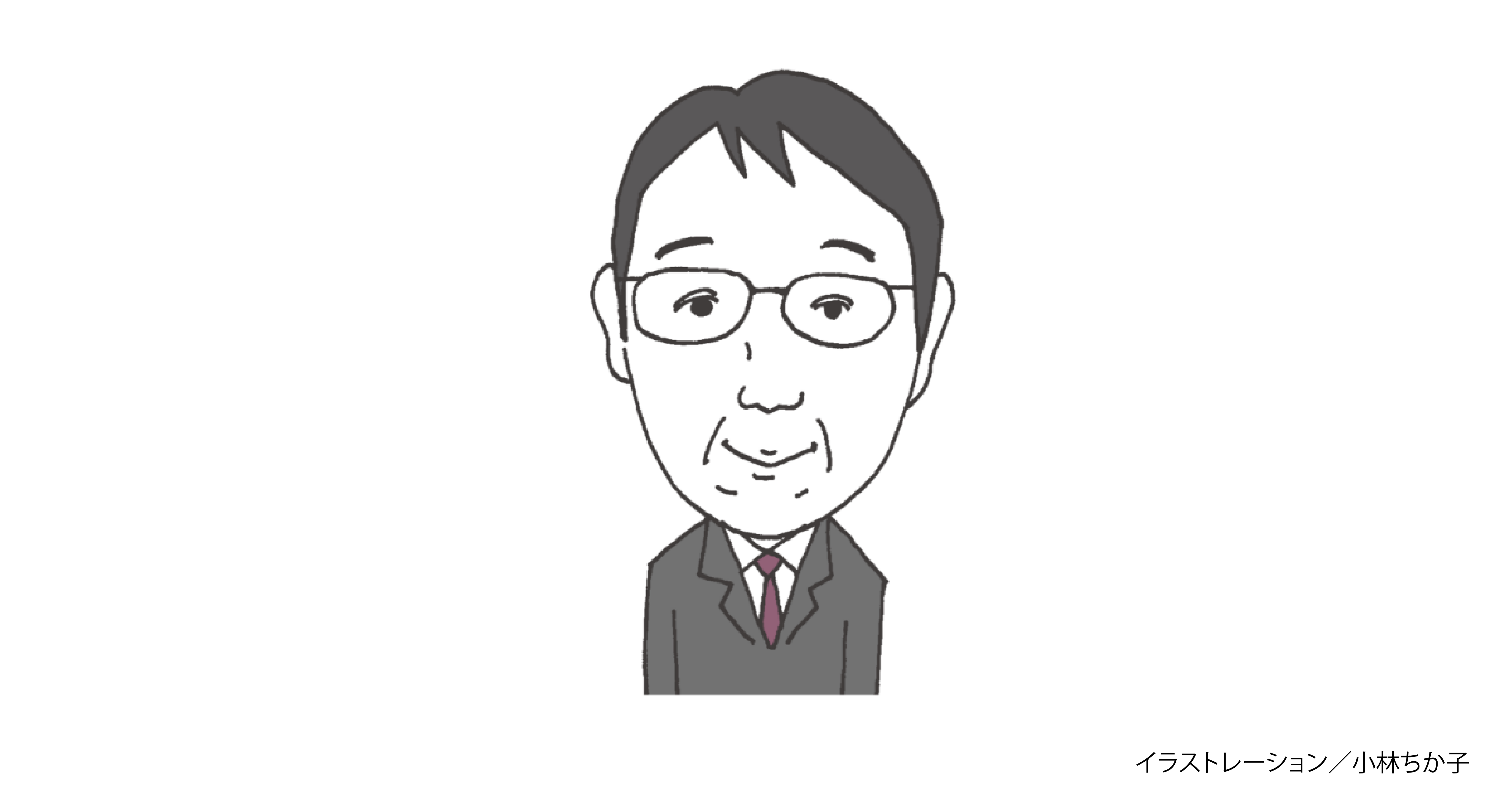2025.04
持続血糖モニタリング(CGM)から得られるデータの読み方とは?
CGMを使うと、手軽に詳しく血糖値の推移を知ることができます。 CGMから得られるデータの読み方や生かし方について、西村理明先生に教えていただきました。

にしむら りめい
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
この記事の内容
はじめに
日本では2010年に、持続血糖モニタリング(CGM:continuous glucose monitoring)が保険適用となりました。しかしながら、導入当時のCGMは、測定が終わった後にさかのぼって血糖変動を確認するタイプだったため、糖尿病の専門施設などで細々と使われていました。
この流れが大きく変わったのが17年です。新しいタイプのCGM(間歇スキャン式CGM:isCGM)が登場したのです。isCGMでは、センサーを専用のリーダーでスキャンすると、その時点までの血糖値の変動がすぐに確認できます。これにより、患者さん自身が日常生活の中で簡単に血糖値の推移をチェックできるようになりました。本機器の使用が保険適用となる1型糖尿病やインスリン治療中の2型糖尿病のある人においては、より手軽に、より詳しく血糖値の推移を知ることができるようになったのです。
保険適用とならない人でも、医療機関によっては、選定療養という制度を生かして、自費にはなりますがCGMを行うことも可能になりました。また、複数のインターネット通販や一部 キーワードで探す タグで探す 記事作成者で探す関連記事