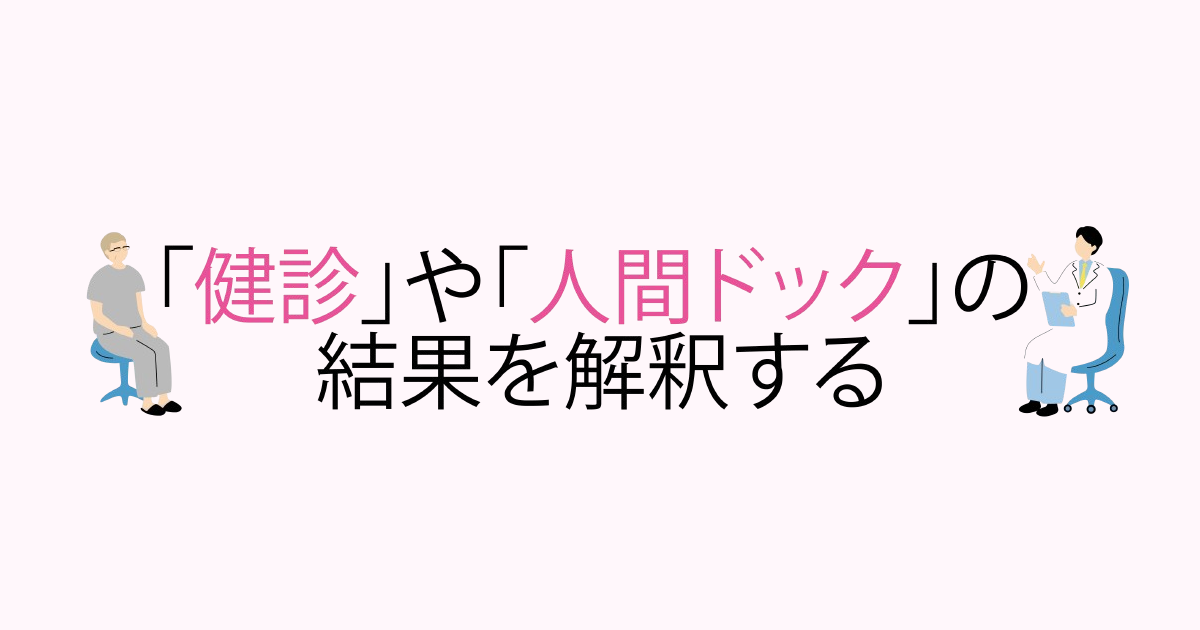2025.10
【第4回】「健診」や「人間ドック」の結果を解釈する
血液検査結果の見方2:肝機能・尿酸値
この連載では、健診や人間ドックの結果の解釈に必要な知識をお伝えします。第4回は肝機能と尿酸値についてです。
遠藤 三紀子
えんどう みきこ
NTT東日本札幌病院ドックセンターセンター長・糖尿病内分泌内科主任医長
この記事の内容
肝機能について
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、自覚症状が出にくいため、機能障害の有無には検査結果のチェックが重要です。表に肝臓の機能を調べるための主な検査項目と基準値を示します。要治療、要精査の判定が最も多い原因は、脂肪肝やアルコール性肝障害で、生活習慣の改善やフォローアップが必要です。肝機能障害の原因が明らかでない場合は、専門医の受診が勧められます。
尿酸値について
尿酸とは、プリン体*が分解されてできる代謝産物です。通常は血液中に溶けており、多くは尿として排出されます。尿酸の血液中の濃度を指す血清尿酸値(尿酸値)が7.0㎎/dLを超えると高尿酸血症といいます。高尿酸血症は食の欧米化により日本でも増加しており、代表的な疾患は痛風です。2022年の「国民健康・栄養調査」によると、痛風の方は135万人、高尿酸血症は1300万人に上ることが分かりました。
尿酸は7.0㎎/dLを超えると血液中に溶けきれず結晶化し、関節や腎臓にたまります。痛風は尿
関連記事
キーワードで探す
タグで探す
- #糖尿病
- #1型糖尿病
- #コラム
- #趣味
- #簡単
- #レシピ
- #写真
- #ライフワーク
- #健口
- #歯科
- #運動
- #治療
- #IDDM Caffe
- #食事
- #さかえ
- #ハイキング
- #フレイル予防
- #体験
- #歯周病
- #撮影
- #継続
- #漫画
- #スティグマ
- #イラストレーター
- #コンビニ食材
- #散歩
- #サイクリング
- #臨床検査技師
- #ウォーキング
- #CGM
- #薬
- #低血糖
- #支援
- #予防
- #運動習慣
- #口腔ケア
- #海外生活
- #診療看護師
- #健診
- #人間ドック
- #高齢者
- #インスリン注射
- #運動の勧め
- #和紙
- #ドイツ
- #表紙
- #開発
- #登山
- #合併症
- #風景
- #仲間
- #高血糖
- #椎原かっぱ
- #千分率
- #神経障害
- #糖尿病治療
- #オーラルフレイル
- #相談コーナー
- #バードウォッチング
- #血糖管理
- #自転車
- #薬剤
- #新薬
- #子育て
- #T1ドクター
- #低山
- #医療従事者
- #糖尿病治療薬
- #糖尿病医療
- #フットケア
- #血液検査
- #透析
- #健康づくり
- #身体活動
- #体験談
- #ダイアベティス
- #減量
- #肥満症
- #サマーキャンプ
- #糖尿病と生きる
- #iPS細胞
- #冷凍野菜
- #熱中症
- #小児糖尿病サマーキャンプ
- #医薬品
- #糖尿病ケア
- #解釈
- #大阪・関西万博
- #パビリオン
- #リハビリ
- #高血圧
- #食事管理
- #ケトアシドーシス
- #糖尿病網膜症
- #睡眠時無呼吸症候群
- #睡眠
- #バードウオッチング
- #足のトラブル
- #運動不足
- #栄養バランス
- #歯周病検診
- #歯周疾患検診
- #肥満症治療薬
- #ストレッチ
- #インスリン治療
- #がんのリスク
- #超音波検査
- #アドボカシー活動
- #高齢者糖尿病
- #BMI
- #一眼レフ
- #インスリン療法
- #隙間時間
- #薬物療法
- #遺伝子
- #お酒
- #腎機能
- #レジスタンス運動
- #血糖変動
- #医療機器
- #動脈硬化
- #イコデク
- #静岡
- #創薬
- #治療薬
- #糖代謝
- #脂質代謝
- #日常
- #ヘモグロビンA1c
- #大災害
- #皮膚疾患
- #皮膚のトラブル
- #血管障害
- #水虫
- #食生活
- #夏の低血糖
- #無自覚低血糖
- #膵移植
- #膵島移植
- #免疫抑制薬
- #JADEC賞
- #糖尿病対策
- #末梢動脈疾患
- #下肢閉塞性動脈疾患
- #足の血管病
- #血管内治療
- #足の末梢動脈疾患
- #自己抗体
- #自己免疫疾患
- #膵島炎
- #膵β細胞
- #糖尿病の歴史
- #糖尿病三大合併症
- #血管新生緑内障
- #糖尿病眼合併症
- #眼科
- #地震
- #リポート
- #DiaMAT
- #災害支援活動
- #能登半島地震
- #睡眠時間
- #ホルモン
- #SAS
- #簡易検査
- #糖尿病患者
- #糖尿病者
- #カウンセラー
- #カウンセリング
- #トレーニング
- #糖尿病外来
- #ケガの対処法
- #いつでも健口生活
- #エクササイズ
- #全身持久力アップ
- #筋力アップ
- #日本全国の散歩道
- #石川県
- #新・相談コーナーせんせい教えてください!
- #医療機関
- #わたしたち臨床検査技師です!
- #血液透析
- #透析患者
- #糖尿病管理
- #賢く付き合おう!健康・医療情報
- #健康・医療情報
- #情報
- #肥満症治
- #健康障害
- #交流
- #海を撮りながら思うこと
- #フットケア外来
- #体操
- #国際医療
- #出産
- #骨
- #骨折
- #人食いバクテリア
- #感染症
- #発症リスク
- #低血糖恐怖症
- #新編集委員長に聞く
- #健康食品
- #食品の安全性
- #機能性表示食品
- #生活
- #交替勤務
- #転倒予防
- #学術集会
- #インスリン作用不足の状態
- #インスリン感受性
- #内臓脂肪
- #糖尿病予防
- #メタボリックサージェリー
- #代謝改善手術
- #外科療法
- #アート
- #サイエンス
- #学術集会
- #むし歯予防
- #口腔健康管理
- #ステロイド薬
- #動脈スティフネス
- #脳小血管病
- #血管管理
- #慢性閉塞性肺疾患
- #COPD
- #炎症性疾患
- #遺伝
- #多因子遺伝
- #遺伝因子
- #ゲノム
- #デジタルツイン
- #年末・年始
- #おせち料理
- #お雑煮
- #透明人間
- #お正月太り
- #水太り
- #野鳥
- #医療チーム
- #合併症予防
- #クレアチニン
- #群馬県
- #草津温泉
- #Diabetes
- #アドボカシー
- #マインドセット
- #偏見にNo!
- #有酸素運動
- #室内向け
- #寿命
- #生命予後
- #平均寿命
- #お菓子レシピ
- #カラダにやさしい
- #チョコレート
- #ラカント
- #歯科保健医療
- #地域医療構想
- #治療サポート
- #食後の高血糖
- #スマートウォッチ
- #スマートデバイス
- #リスク
- #脂質異常症
- #LDLコレステロール
- #中性脂肪
- #URAT1阻害薬
- #尿酸
- #高尿酸血症
- #メタボリックシンドローム
- #口腔機能向上サービス
- #口腔機能低下症
- #後期高齢者歯科健診
- #口腔体操
- #口の機能低下
- #歯周病菌
- #貼り絵
- #医療支援チーム
- #教育入院
- #経口薬
- #花粉症
- #アレルギー性鼻炎
- #ステロイド
- #腸活
- #温泉
- #腸内細菌叢
- #善玉菌
- #がん
- #自動車運転
- #病気
- #影響
- #インクレチン
- #歯科診療
- #ちぎり絵
- #移植
- #最新
- #大阪
- #長居公園
- #インスリンボール
- #注射
- #診療
- #再生医療
- #医療費
- #助成
- #介護施設
- #血管
- #むくみ
- #足
- #リンパ管
- #応急処置
- #めまい
- #季節の変わり目
- #網膜症
- #週1回インスリン
- #下田
- #黒船祭
- #港町
- #カレー
- #糖尿病予備群
- #水分補給
- #シックデイ
- #ストレス
- #緊張
- #ストレス解消法
- #尿検査
- #採尿
- #尿量
- #老化
- #細胞
- #脂肪肝
- #MASLD
- #肝臓
- #豆乳
- #ちゃんぽん
- #災害時
- #薬剤師
- #認知症
- #バランストレーニング
- #学会
- #効果
- #時短
- #夏バテ予防
- #レジャー
- #日焼け
- #西太平洋地区
- #偏見
- #課題
- #臨床試験
- #三島
- #検診
- #結果
- #大阪マラソン
- #プロ野球選手
- #人生会議
- #ACP
- #ジェネリック
- #薬価
- #バイオシミラー
- #アルコール体質
- #減酒
- #食欲
- #肥満
- #筋肉量
- #治療放棄
- #鹿児島
- #垂水市
- #腎症
- #腎臓内科
- #眼底検査
- #防災
- #DiaMAT
- #JADEC賞
- #貢献
- #小児糖尿病キャンプ
- #登山計画
- #持ち物
- #サンドイッチ
- #アラブ首長国連邦
- #トルクメニスタン
- #高知
- #高知城
- #SMBG
- #測定結果
- #手洗い
- #持続血糖測定
- #マレーシア
- #セルビア共和国
- #新潟
- #長岡市
- #髻山
- #青山高原
- #インフルエンザ
- #新型コロナウイルス感染症
- #ワクチン
- #コグニサイズ
- #社会資源
- #介護保険
- #介護
- #肝機能
- #尿酸値
- #油そば
- #慢性腎臓病
- #腎移植
- #お薬手帳
- #海外旅行
- #英文カード
- #欠品問題
- #情報更新
- #ポリファーマシー
- #更年期
- #更年期障害
- #北欧
- #クウェート
- #水炊き
- #京都トレイル
- #東山コース
- #筋肉
- #サルコペニア
- #ダイナぺニア
- #皮膚トラブル
- #足病変
- #スキンケア
- #プラークコントロール
- #週1回
- #新規医薬品
- #便潜血
- #ダイアベティスケア
- #パシフィコ横浜
- #イベント
- #手巻きずし
- #長野
- #松本市
- #朝熊ヶ岳
- #伊勢
- #ダイアベティスDX
- #AI
- #医療
- #テクノロジー
- #便秘
- #副作用
- #診察室
- #ラジオ体操
- #認知症予防
- #血圧
- #心電図
- #ABI
- #歯科健診
- #上肢
- #検査値
- #2型糖尿病
- #分類
- #クラスター
- #早期発見
- #餅
- #三峰山
- #雪山
- #野球場
- #低糖質
- #糖化
- #ヒートショック
- #シックディ
- #CPAP
- #壊疽
- #ライフスタイル
- #体内時計
- #肺がん
- #レントゲン検査
- #CT
記事作成者で探す
- #遠山 朋美
- #太田 晃司
- #金子 美和子
- #船山 崇
- #椎原 かっぱ
- #田口 理穂
- #熊澤 正継
- #山本 道也
- #坂 宗尚
- #萩原 宏美
- #檜垣 靖樹
- #浜野 久美子
- #鈴木 淑子
- #津村 和大
- #山本 恭子
- #HANZO
- #横田 香世
- #任 和子
- #眞々田 賢司
- #窪田 直人
- #野原 栄
- #残松 直樹
- #野見山 崇
- #原田 範雄
- #村上 隆亮
- #鈴木 大介
- #福元 聡史
- #剣持 敬
- #辛 浩基
- #髙瀬 裕志
- #村角 直子
- #渡邊 麻衣子
- #北澤 京子
- #遅野井 健
- #清野 祐介
- #木村 美枝子
- #八幡 和明
- #新井 桂子
- #小山 由起
- #中園 徳斗士
- #戸所 文生
- #山﨑 真裕
- #近澤 珠聖
- #阿部幸子
- #小林 庸子
- #中川 裕美
- #川本 恵美
- #吉田 陽
- #大津 義晃
- #小坂 喜太郎
- #和田 崇子
- #村上 真珠美
- #安西 慶三
- #宮田 英利
- #小出 知史
- #西村 一弘
- #豊島 麻美
- #佐藤 文紀
- #近藤 琢磨
- #檜垣靖樹
- #新見 麻友子
- #白濱 龍太郎
- #下浦 雄大
- #高橋 大
- #能宗 伸輔
- #田辺 真実
- #渡邉 慧
- #皆藤 章
- #石澤 正博
- #草間 佑美子
- #前田 泰孝
- #渡部 奏
- #田上 展子
- #花田 豪郎
- #内藤 仁嗣
- #小川 渉
- #佐々木 章
- #宮城 朋
- #石田 明夫
- #遠藤 萌
- #高田 浩子
- #門脇 孝
- #清野 裕
- #「さかえ」制作室
- #岩岡 秀明
- #安田 和基
- #坂根 直樹
- #大部 正代
- #堀 陽菜子
- #田﨑 亜矢子
- #矢野 裕
- #髙木 あけみ
- #笠原 剛敏
- #三浦 絵美梨
- #中村 二郎
- #小園 亜由美
- #東内 昭江
- #中村 昭伸
- #廣田 勇士
- #澤田 正二郎
- #武田 美都里
- #名越 智古
- #平野 浩彦
- #佐藤 直美
- #岡野 光博
- #谷 長行
- #小島 太郎
- #庭野 亜美
- #井泉 知仁
- #北谷 直美
- #かっぱ
- #中村 小百合
- #藤倉 純二
- #西村 理明
- #恩田 美湖
- #橘 優子
- #田口 昭彦
- #谷澤 幸生
- #三宅 康史
- #岡本 昌之
- #杉山 雄大
- #綿田 裕孝
- #佐藤 まり重
- #下野 大
- #山下 真
- #西 雅美
- #宿谷 賢一
- #勝海 悟郎
- #高橋 宏和
- #内田 慧月
- #山田 悟
- #和田 啓子
- #数胴 美穂子
- #矢部 大介
- #山﨑 望
- #谷本 真理子
- #川上 純一
- #石田 卓矢
- #吉本 尚
- #岩﨑 有作
- #富岡 一俊
- #大倉 瑞代
- #田淵 仁志
- #佐藤 伸輔
- #伊藤 千賀子
- #權野 博
- #山﨑 裕自
- #本田 佳子
- #安倍 純
- #黒江 彰
- #大塚 洋
- #郷田 秀樹
- #釣谷 大輔
- #河野 千尋
- #渕 慶子
- #武藤 達也
- #浅田 史成
- #近藤 裕子
- #錦戸 慎平
- #鈴木 順造
- #藤原 恵子
- #羽賀 達也
- #矢野 礼子
- #加藤 則子
- #横田 太郎
- #丸山 順子
- #栁原 克紀
- #加勢田 富士子
- #辻本 勉
- #秋山 滋男
- #山本 多恵
- #稲垣 美智子
- #柳澤慶香
- #堂川冴子
- #髙嶋法子
- #大石麻衣
- #山口翔平
- #保科早里
- #山田 実
- #草間恵里
- #野島一郎
- #島袋充生
- #中村昭伸
- #大須賀洋祐
- #古川慎哉
- #三宅映己
- #吉成伸夫
- #遠山朋美
- #小河裕樹
- #渡辺 幸子
- #陳 和夫
- #松本 健
- #柴田 由加
- #神谷 英紀